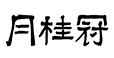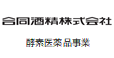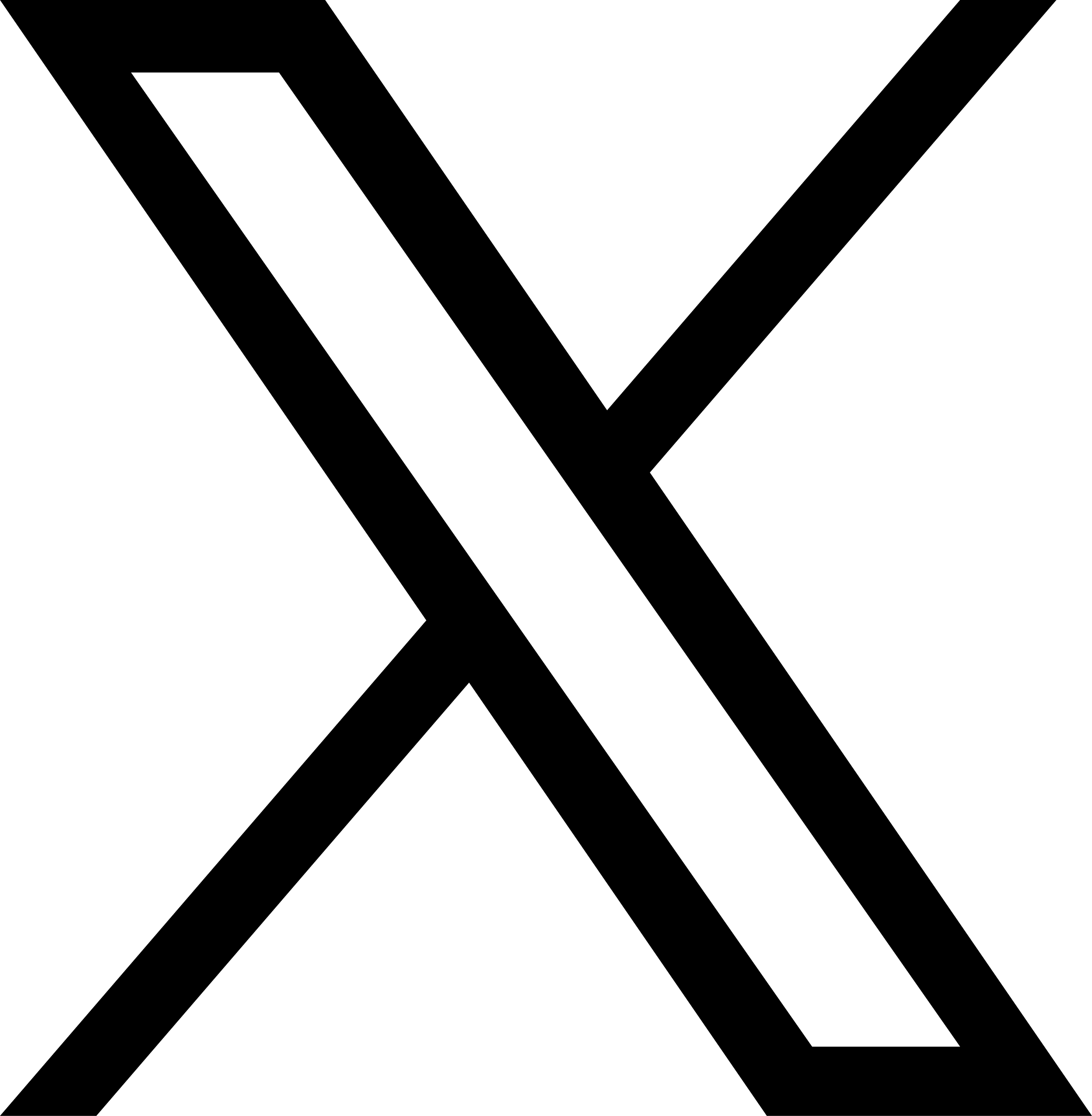「農芸化学」という名前の由来は?
「農芸化学」とは、一般にはちょっと耳なれないことばかもしれません。農芸化学は、生命、食糧、環境の3つのキーワードに代表されるような、「化学と生物」に関連したことがらを基礎から応用まではば広く研究する学問分野です。このような学問が共通の研究・教育分野としてここまで大きく発展したのは諸外国には類がありません。さて、この「農芸化学」という呼び名はいつ、だれが名づけたのでしょうか? また、農芸化学はどのようにして日本に定着して、発展してきたのでしょうか?
「農芸化学」は、明治のはじめごろに西欧の学問を導入するにあたって、ドイツ語のAgrikulturchemie、英語のAgricultural Chemistryの翻訳語として使われはじめました。当時から「農産物」に対して「農芸品」ということばはすでにあり、工芸、樹芸、園芸ということばと同じように、たんなる農産物ではなく、それらに技術的な加工を加えたものを意味していたと考えられます。

晩年のリービヒ(1872年)
農芸化学にあたる学問分野を作り上げるのに最も貢献した人は、ドイツの化学者ユスツス・フォン・リービヒ(1803~1873)です。彼は「植物栄養に関する無機栄養説」を確立し、「リービヒの最小律」として知られる説をとなえて、無機質肥料による農業生産の発展に大いに貢献しました。
リービヒは化学、特に分析化学を基本として当時の欧州で社会的に関心の高かったさまざまな問題に取り組み、「農芸(業)化学」だけでなく動物の栄養や病気に関する「動物化学」の研究も行いました[1,2]。彼は、将来的に食品化学、発酵化学、環境化学などを含む大きな学問分野の基礎を作ったといえます。
さて、日本における最初期の農学校である札幌農学校では、明治9(1876)年の開校当初の学課表に、「Agricultural and Analytical Chemistry」という学課がありました[3]。この講義はダビッド・P・ペンハロー(1854~1910)が担当しましたが、当時の札幌農学校の外国人教師による講義は全て英語で行われており、この学課を当時から日本語で「農芸化学」と呼んでいたかどうかは定かではありません。

エドワード・キンチ
それとほぼ同時期に、明治政府は、東京にも本格的な農学校を設立するために、イギリスから各分野の外国人教師を数人呼ぶことにしました。当初の計画ではそのうちの1名として「分析教師」を選ぶことになっていました。
しかし、明治9(1876)年6月にイギリスのサイレンセスター王立農学校のエドワード・キンチ(1848~1920)との雇用契約を結んだときには、その契約書の和訳に「農芸化学教師」として雇う、ということばが記されています[4,5]。これを和訳したのは訳官鈴木宗泰であり、英語の原文は確認されていませんが、いまのところ、これが文書で確認できる最も古い「農芸化学」です[6]。
この頃、Agricultural Chemistryにあたる本や学問は、「農業化学」あるいは「農用化学」などと訳されることも多く、「農芸化学」と混在する時期がしばらく続きました。しかし、化学を農業生産資材や農業加工品、さらには生理学にまで応用する学問においては、しだいに、技術・芸術を意味する「芸」(注)の文字が入った「農芸化学」の方が適当であると考えられるようになったのではないでしょうか。
「農芸化学教師」キンチは明治10(1877)年に来日し、東京・駒場に新設された駒場農学校では「農芸化学」の講義がはじまりました。さらに、同じ年に「農芸化学科」も設立されました。キンチは明治14(1881)年に帰国するまでの間、日本特有の食物、富岡製糸工場の用水、藍染めに使われるインディゴ色素、関西で生産された有機質リン酸肥料のグアノ、品川湾の鮭など、さまざまな農産物や農業資源を分析しており、我が国の農業および農学に大いに貢献しました[7,8]。したがって、駒場農学校および日本に農芸化学を定着させた第一人者はキンチであるといってよいでしょう。
キンチの後任には、ドイツのホーエンハイム農業アカデミーからオスカル・ケルネル(1851~1911)が招かれました。ケルネルは明治14年に来日してから明治26(1893)年に日本を離れるまで駒場農学校で教育・研究を行い、現在の農芸化学につながる学問の基礎を確立した人物として知られています。彼が試験に使用した水田は今でも目黒区駒場野公園にあり、「ケルネル田圃」の愛称で親しまれています[9]。

左から、ケルネル、ロイブ、古在由直、鈴木梅太郎
ケルネル、そしてその後任のオスカル・ロイブ(1844~1941)の門下生たちは、外国人教師が去ったあとも、日本の農芸化学の発展をけん引しました[9,10]。例えば、ケルネルの直弟子である古在由直(1864~1934)は、足尾鉱毒事件の分析調査などを行い、当時の日本で社会的意義の高い研究を展開しています。
そして、ロイブが帰国した18年後、大正13(1924)年7月1日に、日本農芸化学会が設立されました。初代の会長はオリザニン(ビタミンB1)の発見で有名な鈴木梅太郎(1874~1943)です。この時期以降、全国の大学の農学部に農芸化学科が設置されることになります。日本農芸化学会が設立されてから90年以上がたちますが、今日の日本の農芸化学は、欧米のAgricultural Chemistryとは異なる独自の一大分野に発展したといえるでしょう。
2014年7月10日
日本農芸化学会広報委員会(文:伏信進矢)
文献
- [1] 熊澤喜久雄:肥料科学、1、40(1978)
- [2] 熊澤喜久雄:肥料科学、25、1(2003)
- [3] 北大百年史 札幌農学校史料(一)、札幌農学校史料(二)(1981)
- [4] 安藤圓秀編:駒場農学校等史料(東京大学出版会)、pp. 61(1966)
- [5] 熊澤喜久雄:化学と生物、51、566(2013)
- [6] 安藤圓秀:農学事始め(東京大学出版会)(1964)
- [7] 熊澤喜久雄:肥料科学、9、1(1986)
- [8] 熊澤恵里子:農村研究、113,1(2011)
- [9] 熊澤喜久雄:化学と生物、51、638(2013)
- [10] 坂口謹一郎:化学と生物、12,36(1974)
写真出典
- Siegfried Heilenz: “Das Liebig-Museum in Gießen – Führer durch das Museum und ein Liebig-Porträt, aktuell kommentiert”, Verlag der Ferber’schen Universitätsbuchhandlung Gießen (1988)
- 東京農工大学百年の歩み/東京農工大学創立記念事業会編(昭和56年)
- 農学會會報 第19号(明治26年)
- 日本農業教育史/全国農業学校長協会編(昭和16年)
(注)
- 「芸」
「藝」という漢字にはもともと木や草の苗を地面に植えるという意味があります。四書五経によれば、古代中国の学校では貴族の師弟に「六藝(りくげい)」といわれる六種類の教養科目が教えられていました。人の精神に何かを芽生えさせ、花開かせ、心の中に豊かに実り、大きな収穫を得させてくれる学問をあらわす文字として「藝」が使われていたといえます。
一方で、「芸」という漢字は、「藝」とは全く関係ない「香りのよい草」という意味の文字として古くからありました。しかし、「芸」は「藝」の上下を組み合わせた形であるため、日本では早くからこの文字を「藝」の略字として使い続け、戦後に定められた当用漢字でも「芸」は「藝」にかわる規範的な漢字とされた、という経緯があります。
参考:「「藝」が「芸」になったわけ」阿辻哲次 日本経済新聞日曜版(遊遊漢字学から引用)2017年11月5日
創立当時の学会名称:日本農藝化學會(大正13年7月1日)