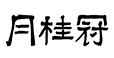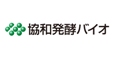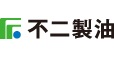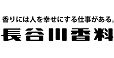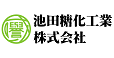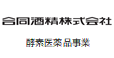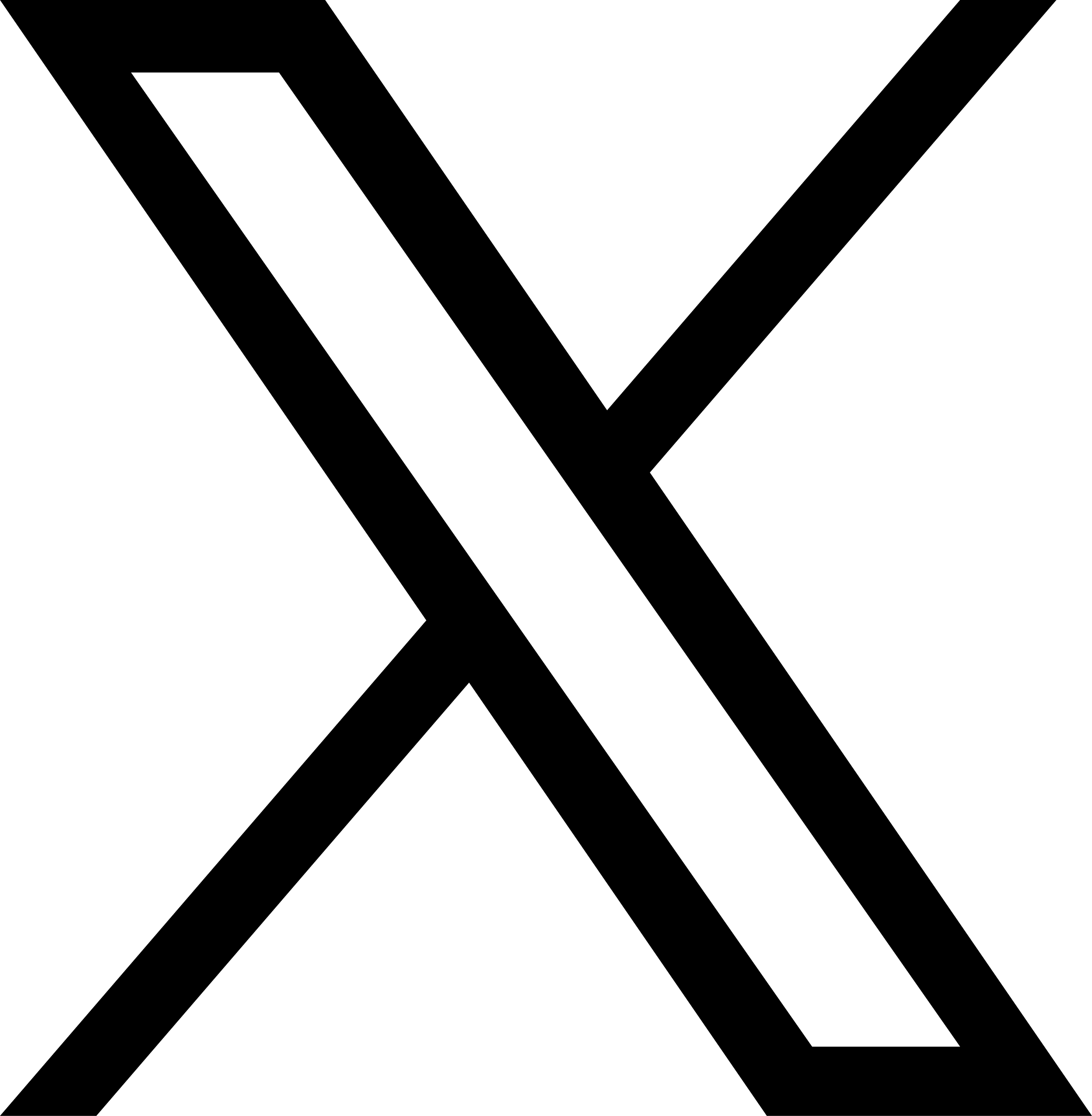Frontiersシンポジウム
学部生・大学院生をはじめ、大学・企業・研究機関の若手研究者を対象としたシンポジウム及び交流会で、研究分野や世代を超えた参加者相互の交流を促すことを目的としています。
これからの開催予定
| 年度 | タイトル | スピーカー(所属) | 日程 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|
| 第31回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:松宮健太郎(京都大) | ||||
| 2026 | (演題未定) | 川田 裕美 (ヘッジホッグ・メドテック CEO) |
3月12日~3月13日 | 同志社びわこリトリートセンター |
| (演題未定) | 脇坂 聡 (グリコ栄養食品株式会社・総務人事部長) |
|||
| (演題未定) | 小川 静香 (株式会社サイキンソー・Chief Financial Officer Member) |
|||
| (演題未定) | 北野 隆司 (近畿大学 産業理工学部・准教授) |
|||
| (演題未定) | 西川 慧 (タカラバイオ株式会社・CDM推進部専門部長) |
|||
| (演題未定) | 山口 庄太郎 (天野エンザイム株式会社・イノベーション本部長) |
|||
過去の開催
| 年度 | タイトル | スピーカー | 日程 | 開催場所 |
|---|---|---|---|---|
| 第30回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:田上貴祥(北海道大) | ||||
| 2025 | 君は何によって憶えられたいか | 良知 博昭 | 3月8日~3月9日 | 札幌北広島クラッセホテル |
| 有機化学YouTuber:続ける理由 | もろぴー[諸藤 達也] | |||
| 農芸化学者のいきる道 | 神 繁樹 | |||
| クマは人類に健康をもたらすか? 過食と絶食を繰り返すクマのお話 | 下鶴 倫人 | |||
| 母子栄養の研究者が取り組む社会実装への挑戦 | 金高 有里 | |||
| 腸内細菌叢=あなたの体質?! 最新“腸”科学が解き明かす個人差と腸内環境の関係性 | 福田 真嗣 | |||
| 第29回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:藤井壮太(東京大) | ||||
| 2024 | 限界環境で生きる微生物を追いかけてロックな研究していたはずがなぜか会いに行けるアイドルになり体制側で出世していた男の話 | 高井 研 | 3月27日~3月28日 | クロス・ウェーブ府中 |
| 植物細胞の形に対する画像解析と人工知能によるアプローチ | 朽名 夏麿 | |||
| 記憶制御基盤の解明と農学と医学への応用 | 喜田 聡 | |||
| 微生物のデジタル機能解析へのアプローチ:必要から生まれる技術 | 竹山 春子 | |||
| 「やってみなはれ」精神で挑んだ夢の青いバラの開発 | 中村 典子 | |||
| バイオリソースとしてのiPS細胞の利活用 | 林 洋平 | |||
| 第28回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:榎本賢(東北大) | ||||
| 2021 | 地方中小企業での研究開発15年と食品添加物を通して見た食品業界 | 阿久津 光紹 | 3月21日 | Zoomウェビナー |
| 企業研究者としての10年を振り返って | 佐藤 勇気 | |||
| 農芸化学出身者が科学の周辺で働いてみた-科学コミュニケーションと科学広報の狭間で- | 遠山 真理 | |||
| ウイルスの社会性、植物の社会性 | 宮下 脩平 | |||
| 植物転写因子の化学制御 | 高岡 洋輔 | |||
| イメージングで生細胞内の代謝物動態を明らかにする | 今村 博臣 | |||
| 第27回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:益田時光(九州大) | ||||
| 2020中止 | 生ビールの製造における微生物検査法の開発 | 浅野 静 | 3月28日 ~3月29日 |
Hotel & Resorts SAGA-KARATSU |
| 芋焼酎の香気生成に及ぼす要因について | 高峯 和則 | |||
| Bioinspired the Next: 生物に学ぶシステムデザイン | 岡本 正宏 | |||
| 異分野融合研究を推進するためには | 岩見 真吾 | |||
| 放線菌の二次代謝に学ぶ | 勝山 陽平 | |||
| 植物の驚異的な環境応答能を支える転写開始点制御 | 松下 智直 | |||
| 第26回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:鈴木道生(東京大) | ||||
| 2019 | iPS細胞を活用した筋疾患に対する治療研究開発 | 櫻井 英俊 | 3月27日 ~3月28日 |
レクトーレ湯河原 |
| 走化性大腸菌の個性と集団行動 | 加藤 節 | |||
| 社会人に必要なスキルとしてのプレゼンテーションとモチベーションの維持向上 | 栗田 佳代子 | |||
| 二次代謝データベースKNApSAcK DBを活用したデータサイエンス | 金谷 重彦 | |||
| 食品の美味しさ設計技術 ープロ料理人の調理技術の科学的解釈の試みについてー | 石井 翔 | |||
| 生命科学研究を志向してホタル生物発光反応を進化させる | 岩野 智 | |||
| 化学と分子進化で考える昆虫の食性と適応 | 永田 晋治 | |||
| 第25回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:兒島孝明(名古屋大) | ||||
| 2018 | アクティブ・ラーニングから見た高校教育改革のいま ー新たな高大社接続の可能性を探るー | 田中 智輝、村松 灯、裴 麗瑩 | 3月18日 ~3月19日 |
ホテル竹島 |
| 一歩前に踏み出せる人材の育成を目指して ~阪大工・ビジネスエンジニアリング専攻の取り組み~ | 清野 智史、倉敷 哲生、中川 貴、森 裕章、武田 裕之、向山 和孝 | |||
| キャリアパス、いろいろ ~博士が社会で活躍中~ | 森 典華 | |||
| 代謝生化学と質量分析 ~ライフサイエンスでどの様に質量分析を活かすか~ | 杉浦 悠毅 | |||
| 農芸化学的な植物体内時計の解析 | 中道 範人 | |||
| 発光生物学のナンデモハカセをめざして | 大場 裕一 | |||
| 第24回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:岸野重信(京都大) | ||||
| 2017 | 食品の機能性研究への期待と課題 | 松永 和紀 | 3月20日 ~3月21日 |
KKR京都くに荘 |
| 異分野をつなぐ懸け橋をめざす | 児林 聡美 | |||
| 科学的であることの価値を考える | 伊勢田 哲治 | |||
| 社会に向けた『科学の伝え方』を考える | 水町 衣里 | |||
| 第23回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:奥山正幸(北海道大) | ||||
| 2016 | ナニガナンダカワケノワカラナイモノとの格闘 | 近森 憲助 | 3月30日 ~3月31日 |
定山渓ビューホテル |
| キラル分光法を用いた生理活性物質・糖・ペプチドの構造解析 | 谷口 透 | |||
| 農芸化学研究者から見た農林水産研究行政 | 西本 完 | |||
| 昆虫共生微生物の研究~さらなる高みを目指して~ | 菊池 義智 | |||
| 感染症の克服を目指して―Girls, be ambitious― | 大西 なおみ | |||
| 植物ホルモン研究最前線と私の研究テーマの変遷 | 浅見 忠男 | |||
| 第22回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:今中洋行(岡山大) | ||||
| 2015 | 深海・地底・南極に地球外生命の可能性をさぐる | 長沼 毅 | 3月29日 ~3月30日 |
ゆのごう美春閣 |
| 昆虫摂食阻害物質アザジラクチンの合成 | 森 直紀 | |||
| 製薬企業研究者のキャリアパス(志と運命の狭間で) | 松岡 正人 | |||
| 実験しない農芸化学 | 田村 隆 | |||
| 食品企業、アカデミア、そして製薬企業での研究を通して | 錦織 伸吾 | |||
| 「生物化学工学」×「動物細胞」=産業化へむけての統合化 | 大政 健史 | |||
| 第21回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:井上順(東京大) | ||||
| 2014 | 製薬企業における創薬研究 | 林 哲 | 3月30日 ~3月31日 |
デュープレックスセミナーホテル |
| 微生物同士の接触刺激による抗生物質生産機構 | 尾仲 宏康 | |||
| 栄養素の不足を感知するしくみ―女性研究者の研究生活 | 竹中 麻子 | |||
| 地球生命の限界から考える宇宙における生命存在可能性 | 高井 研 | |||
| サトウキビからの砂糖・バイオエタノール同時増産システムの開発~農工融合的思考による新たな解決策~ | 小原 聡 | |||
| 食品因子を感知するしくみの解明を目指して | 立花 宏文 | |||
| 第20回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:清田洋正(東北大) | ||||
| 2013 | 製薬業界と企業研究について | 佐藤勇気 | 3月27日 ~3月28日 |
秋保リゾートホテルクレセント |
| 農薬理工医学部(&米国)を渡り歩いて~出会った研究テーマとの向き合い方/異常アミノ酸含有ペプチドのデザインと疾患関連蛋白質阻害剤の創製 | 今野博行 | |||
| 母、妻、研究者 | 西山千春 | |||
| 人為起源物質分解細菌の出現と進化 | 永田裕二 | |||
| 免疫担当細胞の遺伝子転写調節 | 西山千春 | |||
| 抗ウイルス活性を持つプラズマ乳酸菌の発見と食品への応用 | 藤原大介 | |||
| 発明とは既に皆が知っている事象をじっくり見据えて誰も考えたことのないことを考えることである | 大類洋 | |||
| 第19回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:木村泰久(京都大) | ||||
| 2012 | 微生物から魚まで:超チャレンジング研究への挑戦 | 田丸 浩 | 3月25日 ~3月26日 |
聖護院御殿荘 |
| 酵母の基礎研究で20年 | 関藤 孝之 | |||
| 博士号取得から企業研究者へのキャリアパス | 川端 二功 | |||
| 博士課程後の歩み方 ~企業研究者の立場から~ | 柴草 哲朗 | |||
| 食品のケミカルバイオロジー~息子たちの命を守る化学を目指して~ | 齋藤 安貴子 | |||
| 植物代謝とその制御:女性研究者アカデミックキャリアの一例として | 丸山 明子 | |||
| 科学と社会とのあいだに立って、視点の違いを見つける、楽しむ | 水町 衣里 | |||
| 第18回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:永田晋治(東京大) | ||||
| 2010 | miRNAはどのようにしてエフェクター複合体を形成するのか? | 泊 幸秀 | 3月26日 ~3月27日 |
東京大学検見川セミナーハウス・総合運動場 |
| オートファジー(自食作用)その破綻から分かったこと | 小松雅明 | |||
| 植物のホウ酸トランスポーターの機能と細胞内輸送 | 高野順平 | |||
| アブラナの自他認識におけるDNAメチル化の役割 | 柴 博史 | |||
| ArchaeaにおけるType III Rubiscoの機能解明 | 佐藤喬章 | |||
| 高い目標を立てて、努力して、それを実現する | 秋山康紀 | |||
| 第17回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:善藤威史(東京大) | ||||
| 2009 | 科学とコミュニケーション | 元村有希子 | 3月29日 ~3月30日 |
レイクサイドホテル久山 |
| ポストバイオアルコールを目指したアセトン・ブタノール発酵 | 小林元太 | |||
| カイコ突然変異系統を宿主に用いたタンパク質生産技術 | 日下部宜宏 | |||
| 細胞が蛋白質ジスルフィド結合を創りだす巧妙な仕組み | 稲葉謙次 | |||
| 異分野連携の薦め | 井上 豪 | |||
| 第16回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:岩崎雄吾(名古屋大) | ||||
| 2008 | 難培養・極微量・不安定 – 菌根共生シグナル同定を阻む三大困難の克服 | 秋山康紀 | 3月29日 ~3月30日 |
ホテル オースプラザ |
| 動物が季節を感知する仕組みを探る – ゼロからの研究生活 | 吉村 崇 | |||
| 微生物の探・観・拓 | 小川 順 | |||
| 農芸化学的嗅覚研究 – 農から脳へ、脳から農へ – | 東原和成 | |||
| 「- ナチュラルバリエーション – 何か役立つの?」 | 芦苅基行 | |||
| 産業用酵素 – 研究開発から商品化まで – | 山口庄太郎 | |||
| 黄色い花もいかが? – 黄色フラボノイド「オーロン」の生合成と花色改変技術への利用 | 中山 亨 | |||
| 第15回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:小川哲弘(東京大) | ||||
| 2007 | ものつくりのサイエンス(分科会1) | 3月27日 ~3月28日 |
箱根湯本ホテル | |
| コムギ胚芽無細胞タンパク質合成系を活用した研究例 | 牧野伸一 | |||
| 遺伝子組換え酵母による新しい乳酸生産技術 | 石田亘広 | |||
| 見るサイエンス(分科会2) | ||||
| バイオイメージングにおける異分野融合 | 三輪佳宏 | |||
| 複合体X線結晶構造から考える蛋白質分子のダイナミクス | 栗栖源嗣 | |||
| 現場で起こるサイエンス(分科会3) | ||||
| ビール混濁乳酸菌のホップ耐性および関連する微生物管理問題 | 鈴木康司 | |||
| 土壌・地下水を対象としたバイオレメディエーション技術の適用事例 | 高畑 陽 | |||
| シンポジウム | ||||
| 糖鎖によるタンパク質の品質管理機構 | 吉田雪子 | |||
| 輸送体を使って植物をよく育てる | 藤原 徹 | |||
| 翻訳後修飾を受けた生理活性ペプチド | 坂神洋次 | |||
| 第14回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:由里本博也(京都大) | ||||
| 2006 | アフリカの砂漠に生育する野生スイカ – その悪環境ストレス耐性を探る | 明石欣也 | 3月28日 ~3月29日 |
関西セミナーハウス |
| DNAメチル化による胚発生エピジェネティクス制御 | 岡野正樹 | |||
| フコイダンの研究 | 酒井 武 | |||
| 増殖・死滅・分化・癌化と外部環境ストレス | 高木昌宏 | |||
| 緑茶カテキン受容体を介したカテキンシグナリング | 立花宏文 | |||
| マルチターン飛行時間型質量分析計の開発とその応用 | 豊田岐聡 | |||
| 優良微生物の創り方を考える | 宮奥康平 | |||
| 植物抵抗性誘導剤チアジニルのイネ体内動態特性といもち病防除効果 | 八十川伯朗 | |||
| 第13回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:橋床泰之(北海道大) | ||||
| 2005 | Functional triterpenomics’ 多様な植物メタボリックシステムにどう取り組むか?(植物ってこんなに奥深い) | 村中俊哉 | 3月30日 ~3月31日 |
かんぽの宿・小樽 |
| 南極に行こう! – 南極湖沼の微生物 – (北の大地からの最新技術、その1) | 澤邊智雄 | |||
| オキナワモズク由来フコイダンの胃機能改善効果と製品化について(企業発フロンティアへの期待、その1) | 長岡正人 | |||
| イリジウム錯体触媒を用いる環境調和型酸化反応(ノーベル賞研究室で学んだフロンティア) | 鈴木健之 | |||
| ミヤコグサの鳴り響く草原(共生システムってこんなに奥深い) | 川口正代司 | |||
| 技術力、販売力、マーケティング力のバランス(企業発フロンティアへの期待、その2) | 牧 与志幸 | |||
| 分岐の多い多糖類の調製とその特性(北の大地からの最新技術、その2) | 佐藤敏文 | |||
| 第12回農芸化学Frontiersシンポジウム 世話人代表:矢中規之(広島大) | ||||
| 2004 | 醸造微生物の深淵を探る | 秋田 修 | 3月31日 ~4月1日 |
宮島グランドホテル |
| RNAi技術とショウジョウバエゲノム機能解析 | 上田 龍 | |||
| 遺伝子組換えによる花の色の改変 | 勝元幸久 | |||
| 酵素のスクリーニングはオールドバイオ?ニューバイオ? | 加藤康夫 | |||
| 毛は再生できるか? | 岸本治郎 | |||
| ピロリ菌感染症に対するプロバイオティクスの開発 | 木村勝紀 | |||
| 海に生育する微生物の生理学 | 為我井秀行 | |||
| 分裂酵母の配偶子膜形成を観る | 中村太郎 | |||
| 第11回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:鈴木市郎(横浜国立大) | ||||
| 2003 | 花を咲かせる遺伝子(花成遺伝子)を求めて | 荒木 崇 | 4月3日 ~4月4日 |
日本大学湘南キャンパス |
| システムバイオロジーによる概日時計機構の解明 | 上田泰己 | |||
| 植物就眠運動への生物有機化学的アプローチ | 上田 実 | |||
| 枯草菌の転写ネットワークの解明をめざして | 小林和夫 | |||
| 走査型プロープ顕微鏡による生体試料観察 | 繁野雅次 | |||
| 第10回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:川井泰(東北大) | ||||
| 2002 | 遺伝子工学的手法を用いた組換え抗体の作製とその応用 | 浅野竜太郎 | 3月27日 ~3月28日 |
浦嶋荘 |
| 発生過程における細胞・器官の運命決定機構 – ショウジョウバエをモデルとして | 岡部正隆 | |||
| 呈色反応方式の細菌検査システム | 小川廣幸 | |||
| ポストシークエンス時代の蛋白質科学、プロテオミクス | 平野 久 | |||
| 第9回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:木岡紀幸(京都大) | ||||
| 2001 | 研究とそれをとりまく国際取り決め | 門脇光一 | 3月23日 ~3月24日 |
コミュニティ嵯峨野 |
| ポストシーケンス時代のバイオインフォマティクス | 五斗 進 | |||
| ポストシークエンス時代の遺伝子操作動物ビジネス | 塩田 明 | |||
| 健康食品“セサミン”の開発・基礎研究からマーケティングまで | 新免芳史 | |||
| 植食者加害ストレスによって植物が生産する情報化学物質の生態系における機能について | 高林純示 | |||
| 醸造微生物は宝の山:清酒麹菌の興味深い遺伝子発現機構について | 秦 洋二 | |||
| 私たちは、味をどうやって感じているのか? | 林由佳子 | |||
| 第8回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:葛山智久(東京大) | ||||
| 2000 | 皮膚色素沈着におけるヒスタミンの関与 – 日焼けとシミの形成メカニズムへのアプローチ | 吉田雅紀 | 4月2日 ~4月3日 |
東京大学薬学部記念講堂 |
| 巨大化微生物細胞:新しいイオン輸送体アッセイ系の開発 | 矢部 勇 | |||
| 酵素の四次元構造 – X線結晶解析で酵素反応の映画は撮れるか – | 加藤博章 | |||
| ポリケチド化合物生合成の分子遺伝学的解析:生合成遺伝子の機能的改変による有用物質生産を目指して | 池田治生 | |||
| ポストゲノム時代の大量情報集約型細胞機能解析手段としてのプロテオーム解析技術 | 高橋信弘 | |||
| バイオテクノロジーと産業・社会 | 中村雅美 | |||
| 生体分子を用いた超分子複合体の構築 | 上田岳彦 | |||
| 第7回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:立花宏文(九州大) | ||||
| 1999 | 次世代農芸化学 | 4月1日 ~4月2日 |
ヘルスC&Cセンター | |
| 生命科学のフロンティア | ||||
| 見逃されていた非メバロン酸経路。その全貌解明への挑戦 | 葛山智久 | |||
| 原核細胞の細胞分裂時にみられる染色体DNAの動的挙動 | 仁木宏典 | |||
| 細胞増殖とゲノム構造 – 細胞はいかにしてその構造を調節しているのか? | 土屋英子 | |||
| ゲノム解析は農芸化学に何をもたらすか | 田畑哲之 | |||
| スフィンクスの謎:シグナリング分子としてのスフィンゴ脂質 | 伊東 信 | |||
| センサー機能を持つリボザイムの設計と遺伝子治療への応用 | 多比良和誠 | |||
| 発見から実用化まで | ||||
| HGF活性化プロテアーゼとそのインヒビター | 下村 猛 | |||
| 造血因子の発見とその医薬化ーエリスロポエチンを中心に | 大橋秀哉 | |||
| バイオ技術と知的財産 – 医薬産業を中心として | 熊谷健一 | |||
| 学際領域としての農芸化学 | ||||
| 生き物の作るヌルヌル、 – 抗がん剤から省エネルギー材料まで – | 北本 大 | |||
| 刺激応答性DNA複合体を用いる遺伝子の分離と発現制御 | 前田瑞夫 | |||
| アンジオテンシン産生酵素キマーゼの純化とクローニング:臨床的背景をふまえて | 浦田秀則 | |||
| 第6回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:森光康次郎(名古屋大) | ||||
| 1998 | 生命現象の分子メカニズム | 4月3日 ~4月4日 |
レイクサイド入鹿 | |
| 高次脳機能とカテコールアミン情報伝達 | 小林和人 | |||
| 海産ポリエーテル毒の活性発現メカニズム | 村田道雄 | |||
| 核内ステロイド受容体における情報伝達の分子メカニズム | 加藤茂明 | |||
| 薬物輸送におけるGS-Xポンプファミリーの役割と分子構造 | 石川智久 | |||
| 細胞応答と情報伝達研究にみる生き物の知恵 | ||||
| 微生物における圧力応答のメカニズム | 加藤千明 | |||
| 高等植物におけるMAP kinase cascades と環境ストレス | 溝口 剛 | |||
| グルコース効果の新視点:lacオペロンの発現制御と環境応答 | 稲田利文 | |||
| 分裂酵母の有性生殖を制御する情報伝達系 | 川向 誠 | |||
| 20世紀の積み残し(環境問題へのアプローチ) | ||||
| 人為起源環境汚染物質の微生物分解 – 基礎から応用へ – | 永田裕二 | |||
| 富栄養化・資源問題と環境バイオテクノロジー | 加藤純一 | |||
| 環境ストレスに強いイネの遺伝子工学 | 坂本 敦 | |||
| 環境・廃棄物問題への視点 – タコ壺的発想からシステム的思考へ | 松田 智 | |||
| 天然物化学分野のパイオニア研究 | ||||
| 花色素アントシアニンの発色と機能 | 吉田久美 | |||
| 海洋天然物の新しい薬理活性 – 沖縄産海綿の生産するagelasphinを母化合物とするKRN7000の開発 – | 名取威徳 | |||
| 植物フラボノイドが生体内で果たす役割は? | 下位香代子 | |||
| プロテインキナーゼCの発がんプロモーター結合部位を含む合成ペプチドの化学的特性と応用 | 入江一浩 | |||
| 第5回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:中山二郎(東京大) | ||||
| 1997 | Fasのアポトーシスシグナルを標的とした抗癌剤の開発 | 片岡之郎 | 4月4日 ~4月5日 |
富士箱根ランド |
| 抗癌剤耐性にかかわる薬剤排出ポンプMDR1とMRP | 植田和光 | |||
| 染色体テロメアと細胞の腫瘍化 | 石川冬木 | |||
| 食品成分と発がん予防~スクリーニングから作用機構解析まで~ | 村上 明 | |||
| これからの食糧供給 | ||||
| コメの遺伝子工学的手法による品質改善のアプローチ | 高岩文雄 | |||
| 食糧としての遺伝子組換え家畜の可能性 – Tgビーフ、Tgミルクはおいしい? – | 徳永智之 | |||
| 植物バイオテクノロジーの動向 – トマトを中心に – | 中田健吾 | |||
| トランスジェニック魚介類の現状と漁業における展望 | 廣野育生 | |||
| 環境に役立つ生物 | ||||
| 吐息は微生物の餌 | 石井正治 | |||
| 有機溶媒存在下で生育する微生物 | 中島春紫 | |||
| ホウレンソウNiRcDNAを導入したトランスジェニック・シロイヌナズナ植物の解析 | 高橋美佐 | |||
| シロイヌナズナ植物におけるグルタミン合成酵素(GS)アイソザイムの役割分担の比較解析 | 有村源一郎 | |||
| 化けるタンパク質 | ||||
| タンパク質のスプライシング | 川崎政人 | |||
| 動く遺伝子の発現における翻訳調節 | 関根靖彦 | |||
| プリオン – 宿主のタンパク質が宿主に感染する? – | 堀内基広 | |||
| 信号をつかむ | ||||
| 植物ホルモン・サイトカイニンの情報伝達 – two component systemの関与 – | 柿本辰男 | |||
| 動物における細胞増殖シグナル経路 – サイトカインのシグナル伝達を中心として – | 増田誠司 | |||
| 三量体Gタンパク質を介した情報伝達の多様性 | 東原和成 | |||
| 分裂酵母におけるras1情報伝達系の解析 | 伯野史彦 | |||
| 第4回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:小林達彦(京都大) | ||||
| 1996 | 不安を計る – 行動薬理学の実際 | 今泉正洋 | 4月2日 ~4月3日 |
コミュニティ嵯峨野 |
| コレステロールと健康 | 佐藤隆一郎 | |||
| 発酵液のクロスフロー濾過と濾過ケークの構造 | 田中孝明 | |||
| アセタール系[1,2] – カルボアニオン転位の開発:糖質の新変換法 | 友岡克彦 | |||
| 植物の環境応答機構 | 平山隆志 | |||
| Theonella属海綿の生物活性ペプチド | 松永茂樹 | |||
| 嫌気的石油代謝細菌とバイオサーファクタント | 森川正章 | |||
| 第3回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:松井博和(北海道大) | ||||
| 1995 | ポスターセッション | 8月3日 ~8月5日 |
大雪山白金観光ホテル | |
| シンポジウム | ||||
| キノコ由来の細胞機能調節物質の生物有機化学的、生化学的研究 | 河岸洋和 | |||
| 形質転換植物を用いるタンパク質の集積機構の解明と応用 | 増村威宏 | |||
| 乳酸菌の動物消化管内への定着ファクター | 向井孝夫 | |||
| 口腔内の一般体性感覚と味覚 | 駒井三千夫 | |||
| 高度好熱菌の遺伝学と分子育種 | 星野貴行 | |||
| 第2回農芸化学若手シンポジウム 世話人代表:中村顕(東京大) | ||||
| 1994 | ポスターセッション | 4月4日 ~4月6日 |
箱根高原ホテル | |
| シンポジウム | ||||
| MAPキナーゼカスケード | 後藤由季子 | |||
| オーキシンで制御される遺伝子群の解析 | 高橋陽介 | |||
| 分裂酵母ゲノムの解析 | 水上透 | |||
| 細胞機能を調節する微生物由来低分子プローブ | 長田裕之 | |||
| 食品蛋白質の機能発現における分子機構-加熱ゲル形成を中心にー | 谷史人 | |||
| 第1回農芸化学若手シンポジウム 世話人:阿部直樹(東北大)、植田和光(京都大)、 長澤孝志(岩手大) |
||||
| 1993 | Session A | 4月2日 ~4月4日 |
蔵王エコーホテル | |
| 酵母の細胞周期を制御するシグナル伝達機構 | 入江賢児 | |||
| 栄養素と生体の相互作用に関わる分子をいかに捕えるか | 福岡伸一 | |||
| 海洋ポリエーテル化合物-微量天然物のNMRによる解析- | 村田道雄 | |||
| 植物細胞における蛋白質の液胞へのソーティング | 松岡健 | |||
| 糖鎖工学事始めーその方法論とねらいー | 竹内誠 | |||
| Session B | ||||
| 「おいしさと栄養」 | ||||
| 美味しさを測る味覚センサー | 池崎秀和 | |||
| 水のおいしさを測るー感覚量測定- | 畑本二美 | |||
| 食肉の熟成とおいしさ | 西村敏英 | |||
| 「海外の植物バイオサイエンス」 | ||||
| アラビドプシスの物理地図と遺伝子 | 河内孝之 | |||
| 種子貯蔵タンパク質遺伝子の発現制御 | 藤原徹 | |||
| 高等植物二次代謝産物の生合成 | 平田収正 | |||
| 「生物機能物質化学の新展開」 | ||||
| 海洋天然物の合成-プロテインフォスファターゼ阻害剤オカダ酸と2,3のテルペンについて | 市川善康 | |||
| 脱皮、変態に関与する昆虫ペプチドホルモン | 片岡宏誌 | |||
| HMG-CoA還元酵素阻害剤ブラバスタチンの発酵生産と生化学 | 芹澤伸記 | |||
| Session C | ||||
| 「小さな微生物の大きな力」 | ||||
| 固定化微生物システムによる有用物質の生産-Strategy and Result- | 園本謙二 | |||
| C-P結合を持つ抗生物質の微生物による生合成とその遺伝子 | 日高智美 | |||
| セファロスポリン系抗生物質の生産菌の分子育種 | 松田昭生 | |||
| 「分化、増殖のメカニズム」 | ||||
| 核内受容体による転写制御 | 加藤茂明 | |||
| cAMP細胞内情報伝達経路とIGF-I細胞内情報伝達経路のクロストーク | 高橋伸一郎 | |||
| 蛍光in situハイブリダイゼーションによるDNA複製系の解析 | 奥村克純 | |||